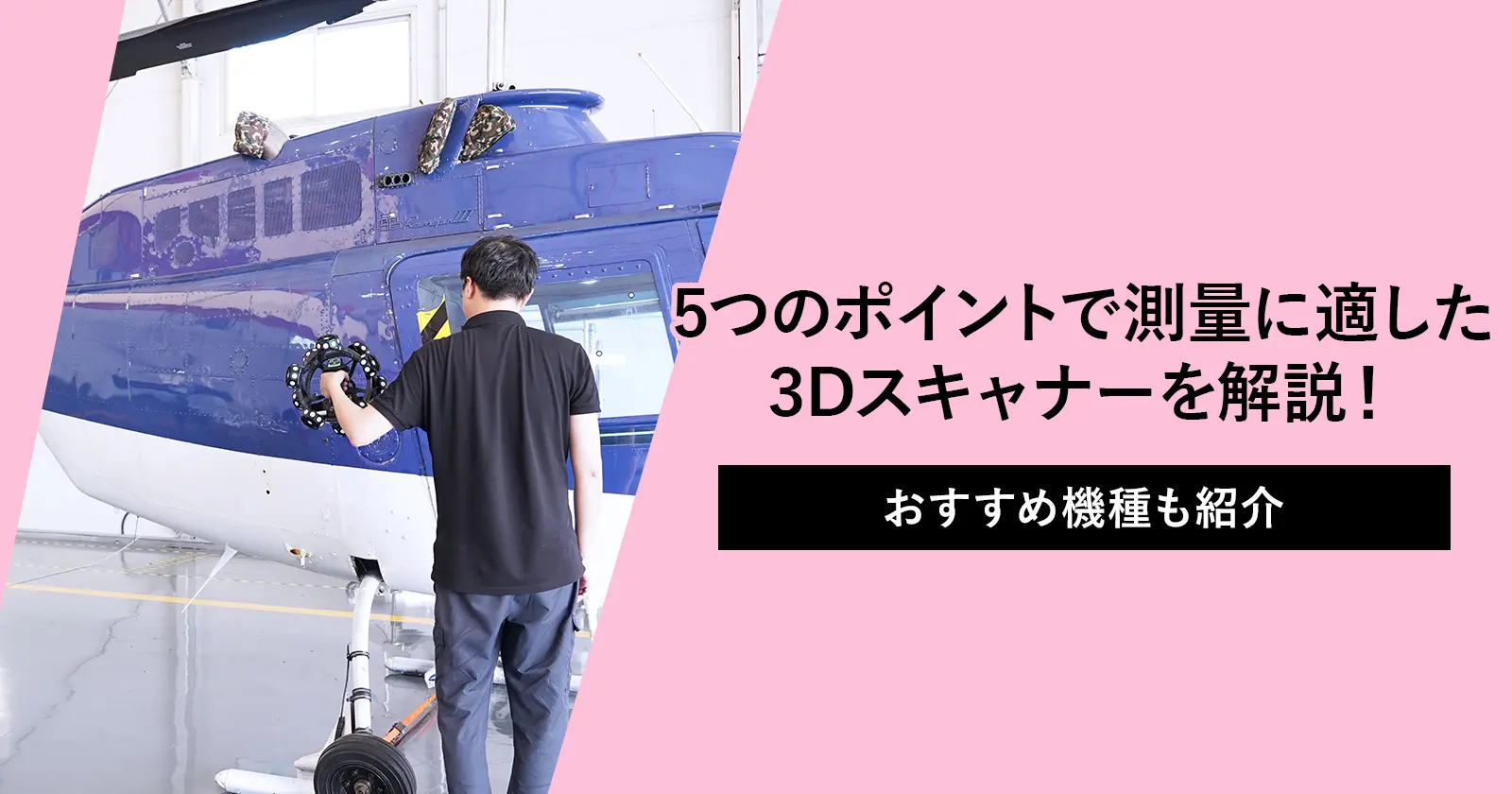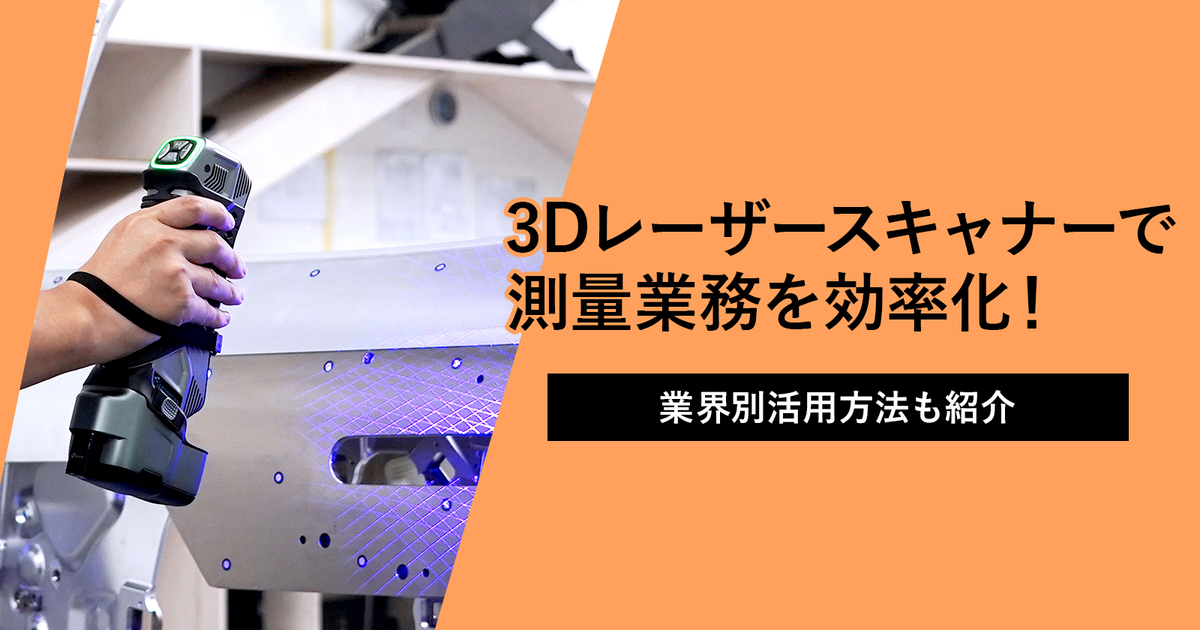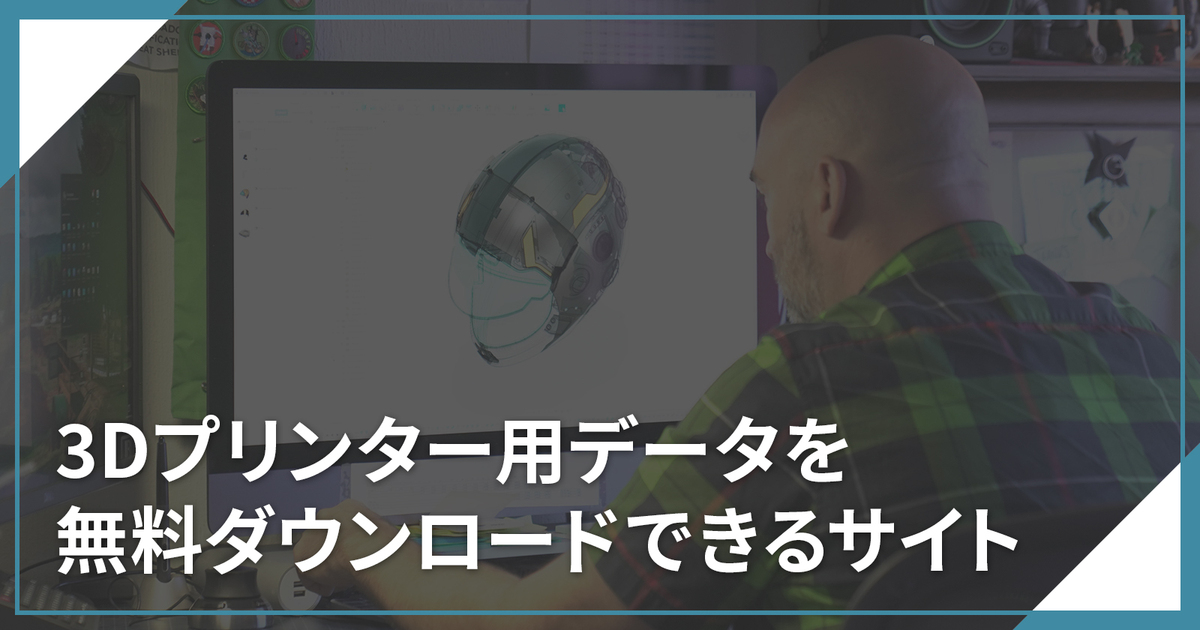3Dスキャナーの原理とは?原理ごとの特徴も紹介
- 3Dスキャナー
- 2025.7.11

3Dスキャナーの原理とは?方式ごとの特徴と選び方
3Dスキャナーは、物体の表面や内部構造を短時間で高精度に取得できる技術であり、設計・解析・製造工程を大きく進化させるキーソリューションです。
本記事では、「3Dスキャナーの原理」をテーマに、代表的なスキャン方式の仕組みや精度の違い、導入時の選定ポイントを専門的かつ分かりやすくまとめました。
目次
1. 3Dスキャナーの基本原理とワークフロー
3Dスキャナーは、主に以下の2つのステップでデータを取得します。
- 形状計測: 光・レーザ・X線などを利用して点群データを取得
- データ処理: ノイズ除去 → ポリゴン生成 → 必要に応じてリバースモデリング
2. スキャン方式の種類と特徴
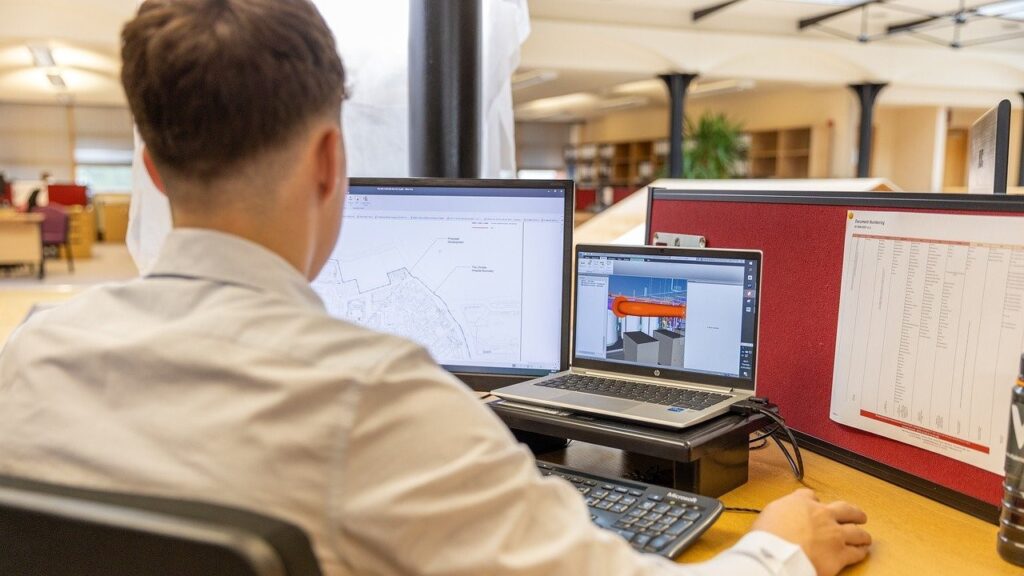
2-1. 接触式 (プローブ/CMM)
機械的な探針で直接測定。
精度 ±2–5 µm、複雑形状に弱い。
2-2. 非接触式
光やレーザーを使って、対象物に触れることなく形状を読み取る方式です。下表に代表的な種類をまとめました。
| 方式 | 原理 | 代表レンジ | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 構造光(三角測量) | プロジェクタ+カメラ2台でパターン光の歪みを解析 | 50 µm–0.1 mm / 0.1–2 m | 金型・歯科・文化財 |
| 多視点フォトグラメトリ | 複数画像の特徴点を三角測量 | 0.1–2 mm / 0.1–100 m | UAV測量・映像制作 |
| レーザ三角測量 | レーザ線+カメラで三角測量 | 10–50 µm / 1 m未満 | 自動車部品検査 |
| 位相差(Phase-Shift)LiDAR | 変調レーザの位相差を計測 | 1–80 m / 1–5 mm | プラント計測・BIM |
| ToF(Time-of-Flight)LiDAR | パルス光の往復時間を計測 | 5 m–1 km / 5–20 mm | 屋外測量・SLAM・自動運転 |
| X線CT | X線透過‐反投影で体積再構成 | 1 µm–50 µm / 約500 mm | 非破壊検査・内部欠陥解析 |
※レンジと精度は代表値であり、機種やキャリブレーション条件により変動します。
3. 原理による精度・速度比較

- 高精度:接触式 ≈ レーザ三角測量 > 構造光
- 広範囲:ToF > 位相差 > 構造光・三角測量
- 内部解析:X線CTのみ対応
4. 3Dデータ取得手順(実践ガイド)
以下の手順で、効率よく3Dスキャンを行うことができます。
- 対象物の固定:揺れやズレを防ぐため安定して設置(小物には回転テーブルが有効)
- 機器設定・キャリブレーション:専用ソフトでスキャナーを初期調整
- スキャン実行:距離や露光を調整して点群取得
- 後処理:不要なデータを除去 → メッシュ化 → 必要に応じてCAD変換
ハンディ型高精度スキャナー SIMSCAN などはワンクリック自動露光機能を搭載し、初心者でも数分でスキャンが可能です。
5. 主な用途・活用事例
5-1. 建築・文化財保存
点群 → BIM モデル化により維持管理コストを 30 % 削減。
5-2. 製造業・リバースエンジニアリング
試作部品をスキャンし Geomagic Design X で 3D CAD 化。
5-3. 医療・人体計測
体表面の歪み評価やオーダーメイド義肢作成。
6. まとめ
3Dスキャナーの選定は、対象サイズ・許容誤差・環境・コストの4要素で決定します。
APPLE TREEでは、お客様の用途に合わせたスキャナー選定から導入支援、操作トレーニングまでトータルにサポートしております。お気軽にご相談ください。